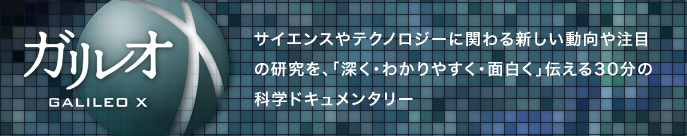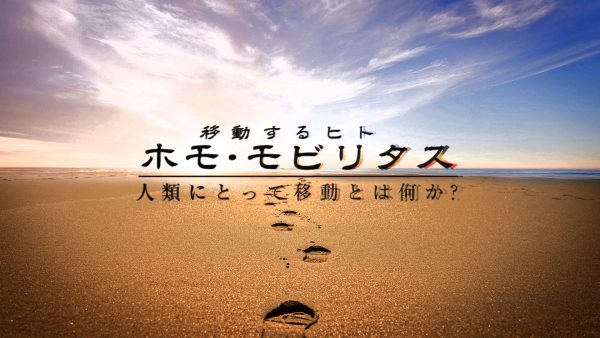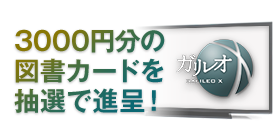移動は人間にとって何を意味するのか?
ホモ・サピエンスの祖先の世界各地への拡散は、他の動物に類をみないものだ。宗教人類学者の植島啓司さんは、ホモ・サピエンスが各地を渡り歩いた経験の蓄積が「自分の外側の世界の認識」へと繋がったのだと言う。例えば、移動の一形態である宗教的な巡礼とは、本来、観光地をまわるようなものではなく、巡礼の過程で何かを見つければそこで旅が終わる、内面的な「移動」であったと言う。さらに宗教の始まりとは、物質世界を超えた「不在のもの」への関心であり、聖地とは人間をその世界とつなぐ場であったのだという。日本の聖地のひとつである熊野も、自然崇拝や祖先信仰から生まれ、多様な宗教が重なり合う移動の結節点として残っている。移動と聖地、この二つが人類の精神史を形づくってきたのだ。
人類はいつ、どうやって移動したのか?
アフリカで誕生したホモ・サピエンスは、やがて陸地の端に至り、さまざまな舟を発明して大海原へと漕ぎ出した。国立民族学博物館教授の小野林太郎さんによれば、アジアとオセアニアの境界には、氷河期の、海面が低下した時期でさえ陸続きにならなかった深い海が横たわっており、人類は舟という道具によって、動物で初めてそれを越えたのだと言う。さらに新石器時代には、外洋航海を可能にした安定性の高い「アウトリガー式カヌー」が登場。文化や技術を伝達する海洋ネットワークの存在が、モアイ像やナンマトル遺跡といった巨石建造物群などの考古学的証拠によって、説得力をもつ。人類は舟によって海とつながり、未知の世界を切り拓いてきたのだ。
ヒトはなぜ、移動をし続ける動物になったのか?
ホモ・サピエンスが、なぜ海の向こうの見えない世界にまで辿り着けたのか。それは、大きな共同体を築き、協力し合えたからだと、総合地球環境学研究所所長の山極壽一さんは語る。そして移動の背景には人類に特有の、三つのエポックメイキングな出来事があったと言う。第一は「直立二足歩行」。樹に登れなくなり捕食者に弱くなった一方、長距離を効率よく歩けるようになり、両手で食料を運び仲間と分け合うことができるようになった。第二は「脳の大型化」。人類は家族と共同体という二重の社会を同時に成立させ、共感力を高めることで見知らぬ集団ともつながれるようになった。そして第三が「言葉の登場」で。情報を共有し、狩りの作戦を立て、未知の土地や海の道を言葉の比喩で伝え合うことで、ネアンデルタール人を凌駕し、大洋すら越えて広がっていったのだと言う。
主な取材先
植島啓司さん(宗教人類学者)
小野林太郎さん(国立民族学博物館)
山極壽一さん(総合地球環境学研究所)
国立民族学博物館