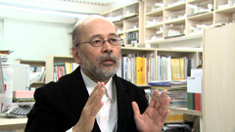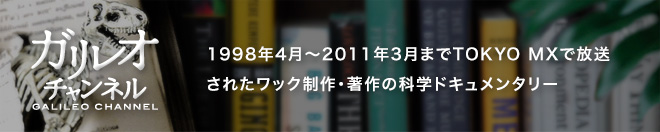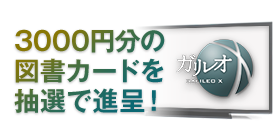京町家の特徴と、ブームの不思議
「仕事場」と「住居」が共存できる構造が京町家の特徴である。この伝統工法による木造建築は汎用性が高く、江戸時代に全国各都市へ広まったが、ほとんどが空襲で焼失し、被害の少なかった京都がその姿を今に伝えている。老朽化が進み、夏暑く、冬寒い京町家がブームになっているのはなぜだろうか?
京町家の「見世」としてのスタイル
見世とは本来「商品を並べて売るところ」の意味だが、現代ではショップやアトリエ、ギャラリーにあたる場所となる。現代の京町家は、SOHOスペースやアートギャラリー、カフェなどに改修されて活用される場合も多い。
京町家の「エコ」のスタイル
伝統工法による自然素材しか使っていない町家は、部分的な改修の手入れもしやすく、それゆえに100年以上住まうことも可能だ。また、古い町家を、断熱性や耐震性に配慮した現代住居へ改築する会社も現れた。
京町家の「コミュニケーション」するスタイル
開放的な京町家には、人が集まりやすい構造がある。公共の場所が失われてる現在、開かれた場所の存在は大きい。コミュニケーションを活性化させる場所としての機能に注目し、食育の活動拠点としたり、ゲストハウスを始めようとしている人々が、豊かなビジョンを語る。
現代の東京や横浜に響く、京町家のスタイル
京町家のもつ多くの機能を現代に再構築するような取り組みが始まっている。東京では集合住宅の中にSHOPやSOHO、コモンスペースを設置するような、開放的で、つながりを重視した建築が完成を控え、横浜では公共の場としてのTOWN CAFEが人と人、人と町をつなぐ場所として自立しはじめている。プライバシーや便利さの追求と引き換えに、現代の都市生活者が失ってしまったものは何であったのか?
主な取材先
東京大学大学院 難波和彦教授
チームネット代表取締役 甲斐徹郎さん
町家倶楽部事務局長 小針剛さん
イータウン代表取締役 斉藤保さん
京町家に住む人々