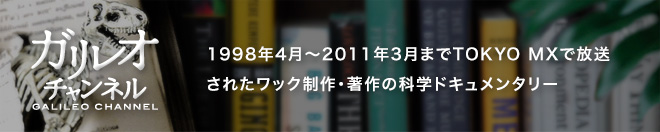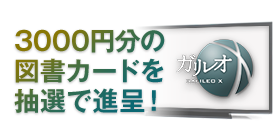小網代の森とアカテガニ
都心から電車で一時間半ほどの距離にある小網代。森と海が川と干潟でつながる小網代は、アカテガニの産卵を見ることができる場所として注目が集まっている。進化生態学者の岸由二さんは、アカテガニを通して森を見ることが、本来の自然の大地のありようを知ることにつながると言う。
自然保護につきまとう間違った自然観
自然を自然のまま放置する。一見、人が関わらない事によって自然は守られているように見える。しかし、都心近郊にある小網代の森のような場所では、自然をそのまま放置すると、生物の多様性が失われていくという。人の手が入らない自然が、生き物と人間にとって一番良い自然であるという考え方は“勘違い”だと岸さんは指摘する。
COP10とSATOYAMAイニシアティブ
2010年10月18日、地球上の様々な生物と生息環境を守ることを目的とした国際会議COP10 が名古屋で始まる。日本は、開催国として「SATOYAMAイニシアティブ」を提案し、世界各国とその考えを共有しようとしている。SATOYAMAイニシアティブとは、日本の原風景「里山」をテーマに生物多様性を保全しようとする試みである。岸さんは、この「SATOYAMAイニシアティブ」は現代にはそぐわないのではないかと疑問を呈する。
自然保護を流域から考える
岸さんは、生物多様性の保全は”流域”をキーワードに進めていくべきだと考えている。流域とは、雨水がどの川に流れこむかを基準に大地を区分けした範囲のこと。流域単位の保全を進めていくためには、市民と行政が一体となり、都市計画の中で行っていくことが必要だという。”流域”をキーワードとした自然保護とはどのようなものかを、鶴見川と小網代の保全活動から探っていく。
主な取材先
岸由二さん(慶応義塾大学/NPO法人小網代野外活動調整会議)