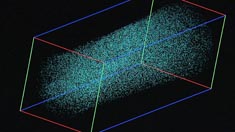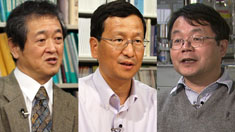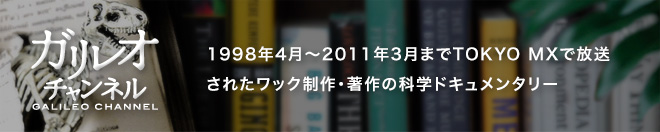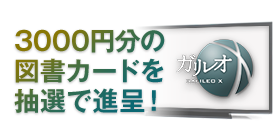世界のインジウムの7割を消費する日本
液晶ディスプレイには、「インジウム」というレアメタルが欠かせない。しかし、インジウムは液晶ディスプレイの製造数の増加とともに、その価格を高騰させている。この問題に対して、インジウムに変わる新材料の研究が始まっている。新材料はチタンという元素で作られる。インジウムに比べ資源量が豊富で低価格のチタンを利用できれば、より低コストで液晶ディスプレイを製造することができるのだ。
電気が流れるセメント?
レアメタルの機能をありふれた物質から引き出す“現代の錬金術”。この夢のような研究に先鞭をつけたのが東京工業大学の細野教授だ。細野教授は、絶縁体のセメントを電気が流れる金属に変えることに成功し世界中の科学者を驚かせた。科学の常識を覆す電気が流れるセメントは、レアメタルを超える新材料として期待されている。なぜこのような材料がつくり出せるのか? 実は物質の性質は元素の種類だけでは決まらないことがわかってきたのだという。
次世代自動車の未来を救え
ハイブリットカーや電気自動車の普及とともに、モーターに使われる磁石の需要が高まっている。自動車で利用される磁石には高温状態でも磁力が落ちない性質が求められるが、磁石にジスプロシウムというレアメタル混ぜることで、それは初めて実現する。ところが、モーターの需要増加によりジスプロシウムの枯渇が世界的に懸念させている。この問題を解決する糸口は、磁石を原子レベルで解析するナノテクノロジーからもたらされた。そこで明らかになったのは、ジスプロシウムは実は必要なかったという驚くべき発見だった。
ありふれた炭素を白金に変える
白金(プラチナ)は、燃料電池のなかで酸素と水素を反応させる触媒として利用されている。この貴金属の中で特に高価な白金のを炭素で代用しようという研究が進んでいる。炭素触媒を実現するために不可欠だったのは触媒メカニズムの解明だった。炭素の原子構造のどこが触媒として機能するのか? 強力な計算能力を持つスーパーコンピュータや物質をナノスケールで観測できるスプリング8によって触媒メカニズムに秘密を解明した研究者に迫った。
主な取材先
原田幸明さん(物質・材料研究機構)
高橋勉さん(ジオマテック)
長谷川哲也さん(東京大学、神奈川科学技術アカデミー)
細野秀雄さん(東京工業大学)
宝野和博さん(物質・材料研究機構)
柿本雅明さん(東京工業大学)
宮田清藏さん(東京工業大学)
寺倉清幸さん(北陸先端科学技術大学院大学)
尾嶋正治さん(東京大学)