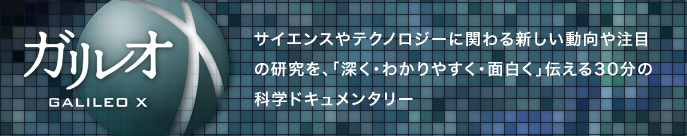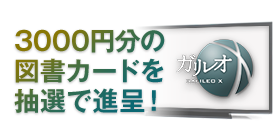水中に残された歴史を紐解く“水中考古学”
人間の活動が刻まれた遺跡は、陸上だけではなく実は水中にも数多く存在している。水中は酸化の影響が少なく、人が足を踏み入れにくい環境であることから、陸上では残りにくいものが保存されやすい環境であるという。これまであまり知られてこなかった水中考古学の調査とは?
2つの矢じりから始まった日本の水中考古学
1908年、諏訪湖の湖底から偶然2つの矢じりが発見された。その後の調査で1万点を超える矢じりや土器が見つかることになる湖底の一角は「曽根遺跡」と呼ばれ、国内初の水中遺跡として注目を集めた。1974年には、北海道江差町沖に沈没した軍艦「開陽丸」の調査が行われ、日本で初めての本格的な水中発掘調査となった。
蘇る蒙古襲来。発見された元寇船
長崎県鷹島沖。この海域は、鎌倉時代に日本が元からの攻撃を受けた蒙古襲来の舞台であり、沈没した元軍の船が眠っていると予想されていた。実際、1980年に始まった発掘から遺物の発見が相次ぎ、2001年にはこれまで古文書でしか知られていなかった元軍の武器「てつはう」が、さらに2011年には元寇船が発見された。蒙古襲来に由来する遺物は何を明らかにするのか?
初島沖に沈む瓦の謎
昨年、伊豆・初島沖の海底で発見された大量の瓦。現在、水中考古学者による調査が行われている。番組のカメラも、海底に横たわる徳川家の三つ葉葵の紋が入った鬼瓦を撮影することに成功した。なぜこの場所にこのような大量の瓦が沈んでいるのか? 水中考古学が紐解く江戸の知られざる歴史とは?
主な取材先
林田憲三さん(アジア水中考古学研究所)
林原利明さん(アジア水中考古学研究所)
中島 透さん(諏訪市博物館)
西谷 正さん(九州歴史資料館)
田中克子さん(福岡市教育委員会)
後藤宏樹さん(千代田区教育委員会)