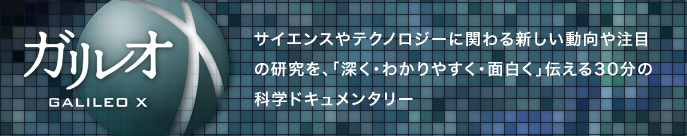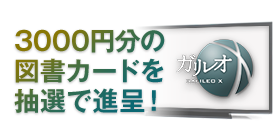すでに身近な遺伝子組み換え食品
日本では、遺伝子組み換え作物の栽培は行われていない。しかし実際には、加工食品の原材料として海外から大量に輸入されており、私たちの多くは既に遺伝子組み換え食品を口にしている。日本に流通する遺伝子組み換え食品とはどのようなものなのか?
遺伝子組み換えとは?
日本でも食用以外の分野では遺伝子組み換え技術による商品化が進み、これまで不可能と思われてきた青いバラや、遺伝子組み換えカイコによる蛍光色に光る絹糸などが誕生している。これまで数千年にわたり人類が行なってた「交配」による品種改良と「遺伝子組み換え」は、どこが違うのか? そもそも遺伝子組み換えはどのように行われるのか?
なぜ遺伝子組み換え食品が必要なのか?
1996年の商業栽培開始以来、南北アメリカを中心として爆発的に生産量が増え続けている遺伝子組み換え作物。すでに、アメリカで作られるトウモロコシの88%、綿花の90%、大豆の94%が遺伝子組み換え作物だという。これほどまでに必要とされる背景とは一体何なのだろうか?
どう付きあっていけばよいのか?
遺伝子組み換え食品に対して抵抗感を感じる人は少なくない。番組が調査した街の声でも、作物の遺伝子に人の手が入っていることへの違和感を訴える声や、摂取による影響が子に遺伝するのではないかという不安の声が上がった。こうした懸念について研究者に取材し、遺伝子組み換え食品と私たちの社会がどう付き合うべきかを探った。
主な取材先
鎌田博さん(筑波大学)
佐藤卓さん(米国大使館)
元木一朗さん(元・理化学研究所)
田部井豊さん(農業生物資源研究所)
佐倉統さん(東京大学)