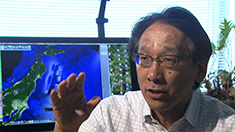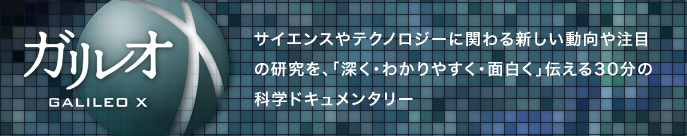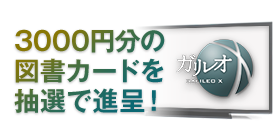防潮堤と防波堤の違いとは?
人々の命や財産を守るために整備されてきた堤防。堤防は防潮堤と防波堤の2種類に分かれる。我々が住んでいる陸側に作られるのが防潮堤。そして、より沖合の海域で整備された防波堤である。そうした設備によって東日本大震災では被害を免れた地域と、壊滅的な被害を受けた地域とに分かれた。
それを分けた要因は何だったのだろうか?
堤防破壊のメカニズム
非常に高さのある津波が到来した時、堤防を越えた陸側に落ちる水が地盤に侵食してしまって倒壊するケースと、強烈な水流に引きつけられて防波堤の表面から破壊される現象が、シミュレーション実験によって明らかになりつつある。そうした破壊現象の発生を防ぐために堤防の構造を根本から見直す試験が行われていた。
「粘り強い」防波堤の実現とは?
津波が越流してしまったとしても、少しでも避難の時間を稼ぐために壊れにくい構造が堤防建設に求められている。
そうした「粘り強い」構造物の実現に向け、堤防を支えるブロックにある工夫を施して抵抗力を増強する実験現場に迫った。
地域に合わせた多重防護の取り組み
東日本大震災で多大な被害を受けた仙台平野は、伊達政宗がまちづくりを始めた400年前にも同様の大津波が襲っていた。そして、より強い地域づくりを目指すための津波多重防護システムがその当時から存在していたのだった。
また今回の津波で高さ20メートルクラスの津波が到来しながら、津波による死者がゼロという岩手県普代村の古くからある巨大水門と現在の津波教育の取り組みから、我々は多重防護をどのように実現することができるのか、その可能性を探る。
主な取材先
今村文彦(東北大学)
佐藤愼司(東京大学)
間瀬肇(京都大学)
諏訪義雄(国土技術政策総合研究所)