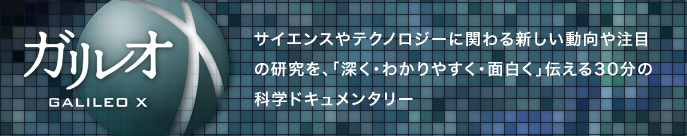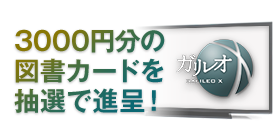激変する世界のエネルギー需給マップ
20世紀末まで先進諸国のエネルギー源として消費されてきた石油の多くはアラブ諸国から輸入されていた。
しかしこの10年ほどで、北米・ロシアをはじめとする天然ガス資源の掘削拡大や、新技術によって生産が可能になったシェールガス、シェールオイルの登場でその資源分布地図が大きく塗り替えられ、中東だけによらない全世界的なエネルギー資源の生産と分配が進んでいる。そして2020年にはアメリカが世界最大の石油産油国になるという。
ドイツの事例からエネルギー政策のヒントを探る
欧米で天然ガスの値段が軒並み下落しているなか、日本では東日本大震災以降、エネルギー源確保のための液化天然ガスが高値で取引されている。長期にわたる日本のエネルギー政策がなかなか見えてこないなか、先進国では初となる脱原発法案を閣議決定したドイツの事例をヒントとして政策を探る。
ドイツでの再生可能エネルギー利用拡大の効果は?
ドイツでは風力や太陽光発電などの再生可能エネルギーで作られた電力を買い取る「固定価格買取制度」が2000年に施行された。この制度により、2012年には再生可能エネルギーの割合が全体の20%強を占めるに至った。
しかし、この買取制度により、全体の電力料金が上昇するという結果に。国際的な経済競争に打ち勝つため、ドイツの大企業では電気料金値上げが免除されるなど制度も整えられたが、その免除を受けられない中小企業との不公平さの解消など新たな問題も生まれている。
日本のエネルギー政策を探る
天候に左右されるという再生可能エネルギーのデメリットを解消するために、ドイツでは従来の火力発電をベースにエネルギーの需給バランスをとるなど、今後も現実を見極めた政策をし続けなければならない。各国が独自のエネルギー政策を推し進めるなか、日本も自国の置かれた状況を具体的に見つめながら、新たなエネルギー政策を見つめていかなければならない。
主な取材先
十市勉(日本エネルギー経済研究所)
朝野賢司(電力中央研究所)
クリストフ・ライヒレ(ドイツ経済産業省)
ミランダ・シュラーズ(ベルリン自由大学)
ロバート・ブライス(ジャーナリスト)