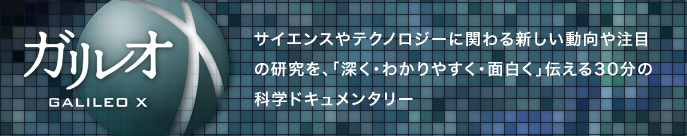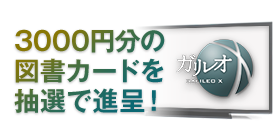電気のゴミ「放射性廃棄物」
原子力発電所の使用済み燃料から生じる「放射性廃棄物」
この“電気のゴミ”は長期間にわたって高い放射能を保持することから、世界各国が処分方法を模索している。自然の放射能レベルにもどるまでにおよそ10万年を要するだけに慎重•確実な処分技術が求められる。エネルギーの大量消費が生み出してきた“電気のゴミ”の処分に向け、研究の最前線ではどのような取り組みが進んでいるのか。
放射性廃棄物処分場「オンカロ」
フィンランド語で“洞窟”を意味する「オンカロ」
南西部の町エウラヨキの地下400mに作られた全長約5kmの大規模な研究トンネルでは、放射性廃棄物の最終処分用地層としての特性調査が最終段階をむかえている。世界に先駆けた研究を行うフィンランドの「オンカロ」を経済評論家の勝間和代氏が訪れた。
日本の“地層処分”研究
今、原子力発電所を持つ各国では既に大量の使用済み核燃料が発生しており、日本でも約17000トンが各原子力発電所の貯蔵プールなどに保管されている。こうした状況 の中、日本でも“地層処分”研究は進められ、火山や地震といった日本特有の環境に適した処分技術が生まれている。はたして日本で地層処分を可能とする技術とはどういうものなのか?
未来に向けた取り組み
私たちが豊かな暮らしを享受するには、生み出される電気のゴミ“放射性廃棄物” の問題から目を逸らすわけにはいかない。この処分問題に向けて私たちが決断すべき選択とは何か、将来に向けた取り組みに今の私たち一人一人が真剣に向き合う事が求められているといえよう。
主な取材先
亀井 玄人(日本原子力研究開発機構)
茂田 直孝(日本原子力研究開発機構)
増田 寛也(野村総合研究所)
オルキルオト原子力発電所(フィンランド)
ポシヴァ社(フィンランド)
雇用経済省(フィンランド)
エウラヨキ町議会議長(フィンランド)