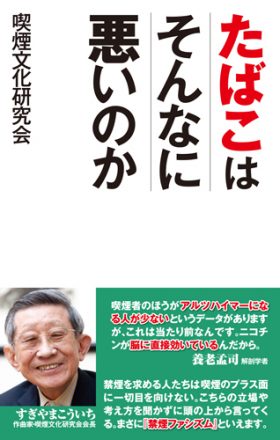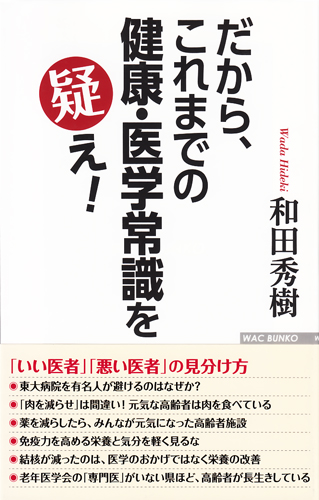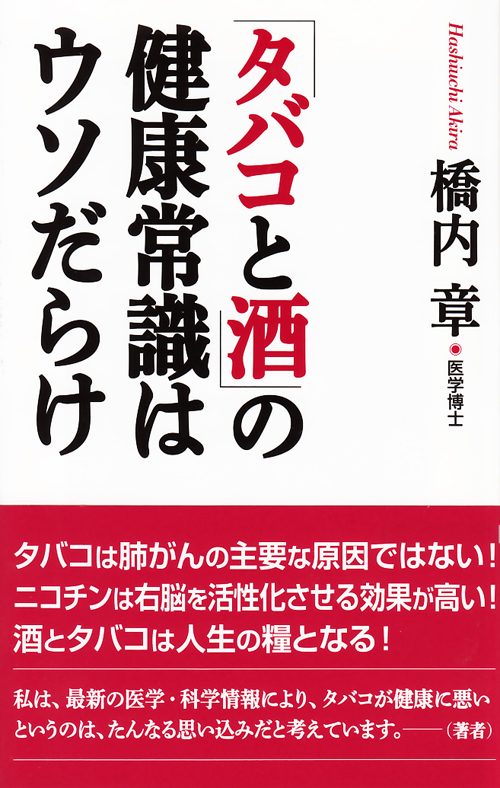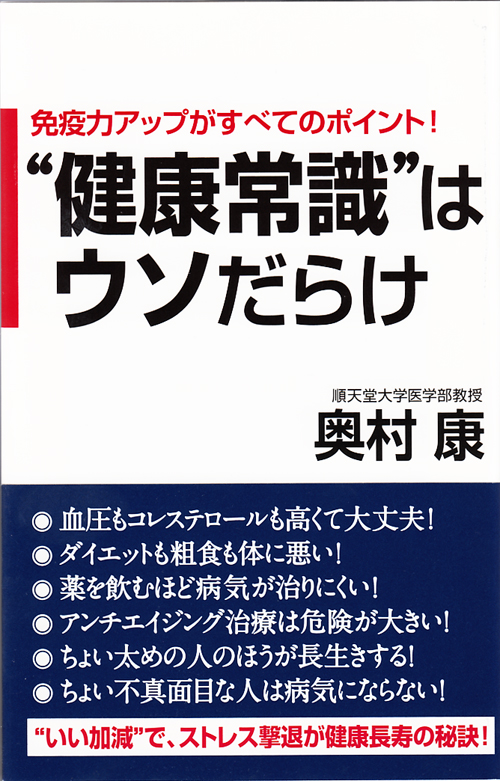著者プロフィール
【喫煙文化研究会】
タバコは文化であると考える喫煙愛好家が集い、会長の作曲家・すぎやまこういち氏をはじめ、養老孟司氏、筒井康隆氏、さいとう・たかを氏、中西輝政氏、西部邁氏等々、各界の文化人、知識人の方々を会員とし、人と喫煙の関係を文化・社会・環境・健康など、さまざまな角度から議論・検討する有志の会。
「美しい分煙社会」をめざし、雑誌『コンフォール愛煙家通信』の発行、「Web版愛煙家通信」公開、シンポジウム開催、分煙推奨番組の企画制作、行政への働きかけ、マスコミへの情報発信など、啓発活動を幅広く行っている。
目次
プロローグ 百害あるものは百利あり
第一部 たばこバッシングの歴史的構造
- Ⅰ ジャパニーズ・パラドックス
- Ⅱ バッシングはいかにして起きたか
- 1 時代背景
- 2 たばこ(喫煙)自体の問題
- 3 たばこ企業に対する批判
- 4 バッシングで「利」を得る勢力がある
- Ⅲ 疫学調査の欺瞞
- 1 統計はウソをつく
- 2 思い込みにもとづく疫学
- 喫煙者と自殺
- 経験の中でモノを見る科学者
- 不利な結果は発表しない
- 3 相関関係は因果関係ではない
- 「関係妄想」という病
- 因果関係は「心の中」だけにある
- 4 因果関係を認める「条件」
- 観察結果の限界
- フィンランド症候群──過剰な健康介入は寿命を縮める
- 5 「因果関係」を推定する五つの「基準」
- (基準①)関連の一致性
- (基準②)関連の強固性
- (基準③④)関連の特異性、時間性
- (基準⑤)関連の整合性
- 6 イデオロギーとなった「科学」
- Ⅳ 「生物医学」というパラダイム
- 1 「還元主義」は有効か
- 地震にもわからないことが我々にわかるはずがない
- 分ければ分けるほど世界はわからなくなる
- 2 社会学からの西洋医学批判
- Ⅴ たばこ企業vs反喫煙主義者
- 1 〝科学的〟な反喫煙運動の始まり
- 2 政治運動としての反喫煙
- 3 州政府の参加がたばこ訴訟を変えた
- 4 世界の喫煙人口は増加する
第二部 たばこはそんなに体に悪いのか
- Ⅰ 喫煙と疾病
- 1 がん
- 半分以上は原因がわからない
- がんは生きとし生けるものの宿命
- 2 肺がん
- たばこ原因説の矛盾
- WHOが衝撃の発表
- 3 自己責任論に隠蔽される環境問題
- Ⅱ バッシングを加速させた〈受動喫煙〉
- 1 〈受動喫煙〉問題の登場
- 2 一万五千人が〈受動喫煙〉で死んだ?
- 3 PM2・5よりこわいという非科学的主張
- 4 憲法より条約を優先するのか
- 5 〈分煙〉で十分
- 6 ドイツでは駅のホームに喫煙コーナーがある
- 7 なぜ〈受動喫煙〉に許容レベルはないのか
- Ⅲ 〈ニコチン依存症〉の〝発明〟
- 1 「習慣性」から「依存性」への誘導
- 2 〝物質の法則〟に還元する理系の人々
- 3 社会的に構築される「病名」
- 4 「DSM」の問題
- Ⅳ もう一つのバッシング「社会的コスト」論
- Ⅴ 「医療化」ということ
- 1 医療の対象となった〈喫煙〉
- 2 「医療化」が拡大する背景
- 「社会統制装置」としての健康管理
- 「医療化」というマーケティング
- Ⅵ 何が人の寿命を決めるのか
- 1 「社会疫学」が示唆するもの
- 仮設住宅が提起する問題
- 「格差」が寿命を縮める
- 「社会関係資本」の重要性
- 人間を見ない〝医療ムラ〟
- 2 長野県が長寿のホントの理由
- 3 アメリカの反省
- 4 「生物医学」パラダイムを超えて
第三部 たばこのチカラ
- Ⅰ 急速に広まった喫煙の風習
- Ⅱ 人は、なぜたばこを吸うか
- 1 科学による〈喫煙〉の説明
- 2 喫煙の効用
- 3 社会関係的効用
- 4 ニコチンの薬理的効用
- 5 身体・感覚的効用
- 触覚(皮膚感覚)
- 嗅覚(ニオイ)
- 視覚、聴覚、味覚
- 6 免疫力を高める
- 7 たばこの利点
- Ⅲ シガレットの「光と影」
- 1 喫煙形態の覇者となったシガレット
- 2 シガレットの「光」
- ニコチン伝達機能の卓越性
- 触覚(皮膚感覚)にもたらす優位性
- その他の優位性
- 3 シガレットの「影」
- 心理的依存を強めたシガレット
- シガレットは〝文明材〟
- Ⅳ 「適正な喫煙」とは
- 1 シガレットの行く末
- 2 無視されがちな用量・用法
- 3 おすすめする吸い方
- Ⅴ 永遠の課題──あとがきにかえて
- (文中敬称略)